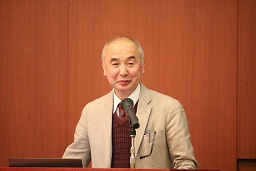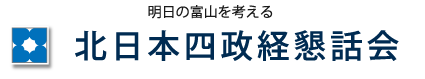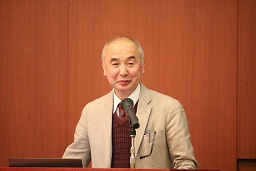にいかわ政経懇話会総会・3月例会
心の拡張性を静める~釈尊の見いだした道~
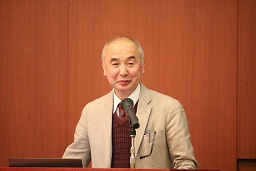
【日時】令和7年3月26日(水)正午~
【会場】ホテルグランミラージュ
【講師】箕輪顕量氏(東京大学大学院社会系研究科教授)
【演題】心の拡張性を静める~釈尊の見いだした道~
お釈迦(しゃか)様が実際に話したことを伝えている可能性があるとされる経典には「足で蛇の頭を踏まないようにするのと同様に、よく気を付けてもろもろの欲望を回避する人は、この世で執着を乗り越える」と記されている。
そのような行為がもたらす結果として、私たちの心が持っている自動的な反応を抑制できるようになる。刺激を受けて心が勝手に起こしていく反応は「第2の矢」とされ、現代的な言葉にすると「心の拡張性」となる。心の自動的な反応を静めるのが「念処(ねんじょ)」と呼ばれる観察の力で、ある時代から「止」と「観」という二つの用語が登場する。お釈迦様の時代は「今の一瞬一瞬に注意を振り向けて十分に把握すること」だけだったのが、時代が下り、確実に注力するために「止」と「観」の二つに分かれたのだろう。現代的な言葉で説明すると、「止」は気付きの対象が一つに限定されて心の働きが静まっているタイプの観察の仕方、「観」は感覚機能が全て生きていて心の拡張性が抑制されていく観察の仕方となる。
今、仏教の瞑想は「マインドフルネス」として市民権を得つつある。次々と気付きの対象を変えていくことによって私たちの自動的な反応は静まるとされる。熟練者は「第2の矢」が起きないような状況に到達できるのだろうが、私たちはなかなかそこまで行けない。それでも大事なのは、悩みや苦しみが生じても、自分の心がつくり出した反応だと気付くようになることだ。さまざまな悩みや苦しみがあっても流せるようになる。これが安らぎの実現につながると考えている。
例会に先立って総会を開き、会長の蒲地北日本新聞社長があいさつ。2025年度の事業計画を承認し、役員改選で新たな副会長に武隈義一氏(黒部市長)、理事に石﨑大善氏(アイザック社長)と杉野岳氏(スギノマシン代表取締役副社長)を選任した。
←前のページにもどる